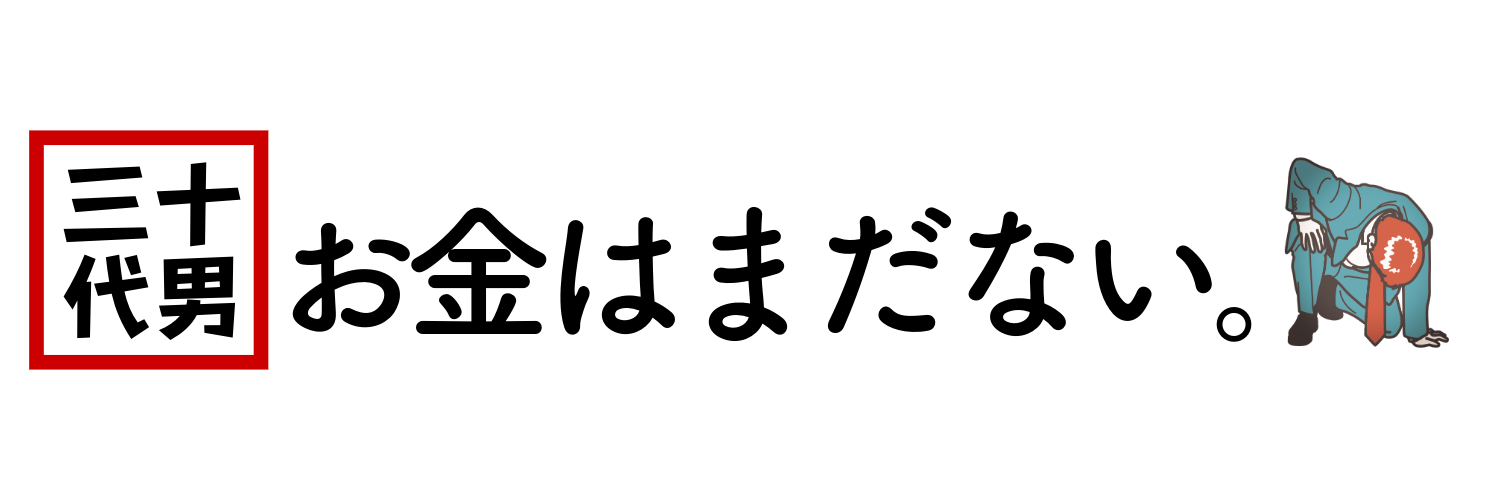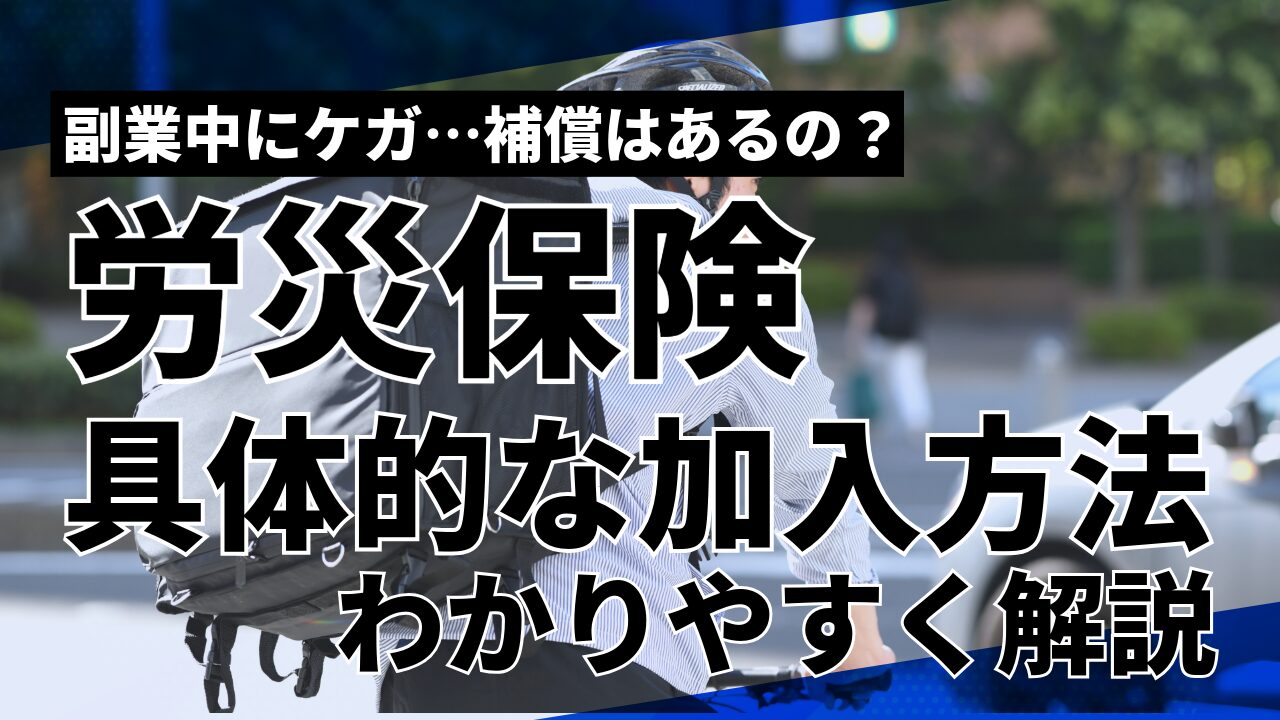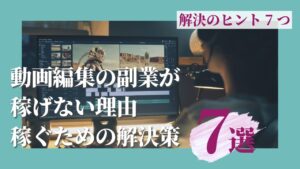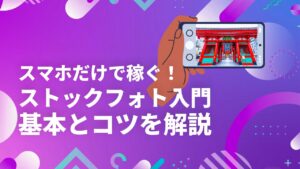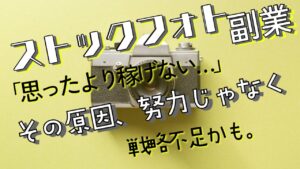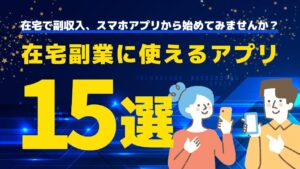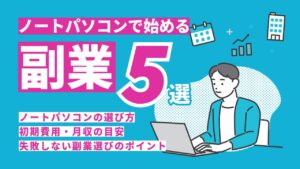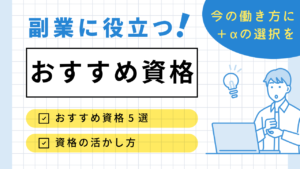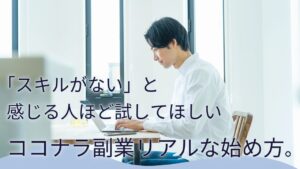「えっ、副業中にケガしても労災って出ないの…?」
そんな声、最近よく聞きます。本業とは別に働く人が増えた今、副業中のリスク対策はもはや“他人事”じゃありません。実は、副業でも労災保険に加入できる制度があるんです。でも手続きはちょっとややこしい…だからこそ、この記事でわかりやすく解説していきますね!
副業でも労災保険に加入できる?まず知るべき基本知識

副業でも、労災保険に「特別加入制度」を利用すれば加入可能です!ただし、誰でも入れるわけではなく、職種や働き方によっては対象外になることもあるので注意が必要です。
まず、労災保険とは、業務中や通勤中に起きたケガ・病気・障害・死亡などに対して、治療費や休業補償などを国が補償してくれる制度です。これは原則として“雇われている労働者”が対象です。しかし、副業で自営業やフリーランス、いわゆる「一人親方(ひとりおやかた)」のように働く場合、通常の労災保険の対象外になります。
そこで登場するのが「特別加入制度」。これは、労働者に該当しない働き方の人にも、一定の条件を満たせば労災保険の加入を認める制度なんです。特に、建設業、運送業、個人請負など“業務リスクが比較的高い職種”で、副業をしている人には心強い制度です。
「え?副業って趣味の延長みたいなものじゃないの?」という方もいるかもしれませんが、配達員や個人ドライバー、動画制作など、今は“仕事として成立している副業”が増えてきていますよね。その分、事故やケガのリスクも本業同様。万が一に備えておくべき時代になっているというわけです。
特別加入には、労働基準監督署の認可や、業種ごとの団体への所属が必要になるケースが多いので、具体的な制度を次章で詳しく解説していきますね!
労災保険に副業で加入する方法【手順と流れを解説】
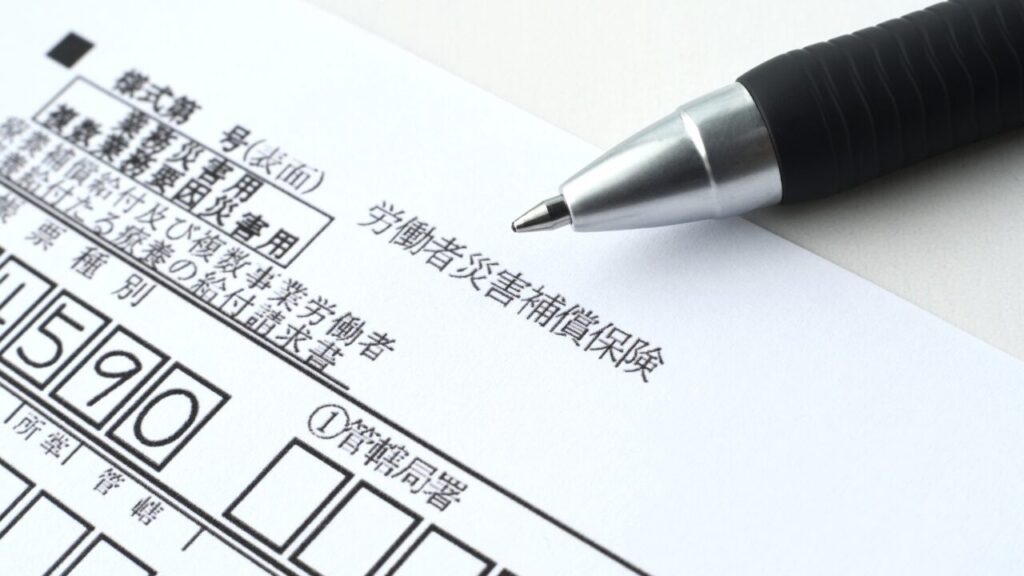
副業で労災保険に加入する方法は、大きく分けて 「特別加入制度を使う方法」と、「民間団体を通じて加入する方法」の2パターンです。どちらを選ぶかは、あなたの副業の業種や働き方によって変わります。
まず「特別加入制度」とは、厚生労働省が定めた制度で、本来、労災保険の対象外である個人事業主や一人親方(例:建設業の個人請負業者)、フリーランス、家内労働者などが、一定の条件を満たすことで国の労災保険に任意で加入できる制度です。
特別加入の大まかな手順
- 業種に対応する「一人親方団体」や「労働保険事務組合」に所属
→ この団体を通してしか申請ができないケースが多いです。 - 必要書類を準備し、労働基準監督署または団体に申請
→ 事業内容や業務実態を証明する書類、本人確認資料などが必要。 - 保険料の支払い(年額一括が多い)
→ 収入やリスクに応じて年間数万円〜の負担が必要です。 - 加入証明書の受領
→ 万が一の事故の際、この証明があることで補償がスムーズになります。
また、2024年から2025年にかけて、マイナンバーと連動したオンライン申請窓口の運用が始まり、労働基準監督署に出向かずに手続きができるようになってきました。これにより、地方在住の副業ワーカーでも加入がしやすくなっています。
一方で、「特別加入」の対象外になる業種や、より柔軟な補償を希望する人は、民間団体が提供する労災型の保険サービスを検討してもよいでしょう。例えばフリーランス協会などでは、業務災害補償のついた保険プランを提供しており、月額1,000円前後で補償が受けられる場合もあります。
「労災保険 加入方法」というと難しそうに感じるかもしれませんが、加入の窓口を正しく選べば、実は手順はシンプル。あなたの副業スタイルに合った方法を選び、早めの備えをしておくことが重要です。
副業の種類別:労災保険の必要性と適用事例

副業の内容によって、労災保険の必要性や適用可否は大きく変わります。
特に「現場作業系」や「外で体を動かす仕事」はリスクが高く、補償の備えがあるかどうかで安心感がまったく違います。
ここでは代表的な副業を例に、必要性と適用されるケースを見ていきましょう。
リスクが高い副業:労災保険が“ほぼ必須”なケース
以下のような職種は、作業中にケガや事故が起こる可能性が非常に高いため、労災保険への加入が強く推奨されます。
該当職種の例:
- フードデリバリー(Uber Eats、出前館など)
- 軽貨物ドライバー(Amazon Flexなど)
- 建設・解体・内装業の一人親方
- 清掃業(ビル・マンション清掃など)
リスクは低いが確認が必要な副業
在宅やパソコン中心の副業は一見リスクが低そうですが、完全にゼロではありません。
該当職種の例:
- Webライター
- 動画編集者
- プログラマー
- オンライン講師
注意点:
- 自宅作業中の転倒や、パソコン作業による肩や腰の慢性障害などは「業務起因性の証明」が難しく、労災が適用されにくい傾向にあります。
- そのため、補償を重視する場合は「民間の業務災害保険」も併用すると安心です。
労災保険の対象外になる可能性がある副業
以下のような副業は、労災保険の適用対象外となることが多いため、事前に確認が必要です。
例:
- アフィリエイト、投資系の副業(肉体労働や対人業務がない)
- 完全なボランティア活動
- 業務実態がなく、趣味の範囲と判断される活動
副業の内容によっては、「入っていないと危ない!」という仕事もあれば、「入ってもほぼ使わないかも?」という仕事もあります。
とはいえ、“万が一”は誰にでも訪れます。あなたの副業の性質に合わせた保険加入の検討が、将来の安心につながりますよ。
「副業 労災保険 加入 どこで」探せばいい?加入先の選び方

「副業で労災保険に入りたいけど、どこで申し込めばいいの?」
──この疑問、実はかなり多いんです。でもご安心を。加入先は大きく2つに分かれます。
労災保険加入先の主な選択肢
国の制度を利用する場合(特別加入)
- 加入窓口:労働基準監督署 or 労働保険事務組合(団体経由)
- 対象者:建設業、運送業、漁業、林業などに従事する一人親方や自営業者
- メリット:
- 国が運営するため信頼性が高い
- 給付の手続きが整っていて、範囲も広い
- デメリット:
- 業種が限定されている
- 団体への加入が必要で手間がかかる場合も
民間団体を通じた加入(フリーランス協会など)
- 加入窓口:団体の公式サイトや申込ページ
- 対象者:業種問わず幅広いフリーランス、副業従事者
- メリット:
- 在宅ワークやデジタル系でも加入できる
- 他の福利厚生(賠償責任保険など)とセットで付いてくる
- 入会・申請がオンラインで完結する場合が多い
- デメリット:
- 国の労災とは制度設計が異なる
- 給付内容に限りがあることも(休業補償の金額など)
自分に合った加入先を選ぶには?
まず、自分の副業が「肉体労働型」なのか「デスクワーク型」なのかを考えましょう。
- 肉体労働型(配達・建設・清掃など)
→ 国の特別加入制度(団体経由)がおすすめ - デスクワーク型(ライター・動画編集など)
→ 民間団体の保険付きサービスを検討
また、2025年現在、オンライン申請が全国的に整備されてきており、マイナンバーを利用してネット上で手続き可能になりつつあります。これにより、時間もコストもグッと抑えられる時代が来ています。
「どこで加入すればいいかわからないから…」と後回しにしていると、いざという時に本当に困ります。
あなたの副業のスタイルに合わせて、最適な加入先を見つけておきましょう!
労災保険の保険料と補償内容をチェック
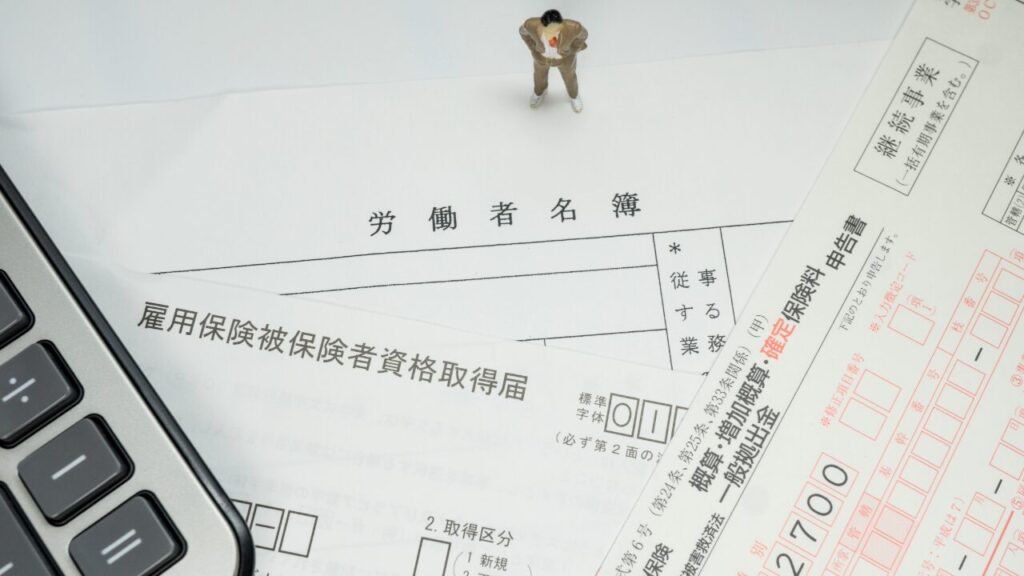
労災保険に加入するなら、気になるのが「保険料はいくらかかるの?」と「どんな補償が受けられるの?」という点ですよね。副業であっても、しっかり補償される体制が整っているのが労災保険の特徴です。
保険料の目安はどれくらい?
副業で労災保険に加入する場合、保険料は年額で1万〜5万円程度が相場です。
これは「特別加入制度」を使った場合で、以下の要素で金額が決まります。
保険料が決まる主な要素:
- 業種ごとの労災リスク(建設業は高め、デスクワークは低め)
- 年間の想定収入額(加入者が選択)
- 選んだ給付基礎日額(3,500円〜25,000円の間で設定)
たとえば、日額5,000円の給付を選んだ場合、年額で約2万円前後の保険料となるケースが一般的です。
※実際の金額は、労災リスクに応じた保険料率・団体の事務手数料・給付日額などにより変動します。
労災保険でカバーされる補償内容
主な補償内容:
- 療養補償給付:業務中のケガ・病気にかかった際の医療費全額補償(自己負担ゼロ)
- 休業補償給付:働けない期間中、給付基礎日額の80%を支給
- 障害補償給付:後遺障害が残った場合の一時金または年金
- 遺族補償給付:万が一死亡した場合、遺族に年金 or 一時金が支給
- 葬祭料:葬儀費用として一定額を補償
これらの給付は、事故が業務中に起きたことが証明されれば適用されます。
国の制度なので、補償範囲が広く、信頼性が高いのもポイントですね。
副業とはいえ、「事故が起きてから考える」では遅いのが現実です。
年間数万円でこれだけの補償を受けられるなら、コストパフォーマンスは非常に高いといえます。
よくある不安と誤解:「副業中は労災が出ない」は本当?
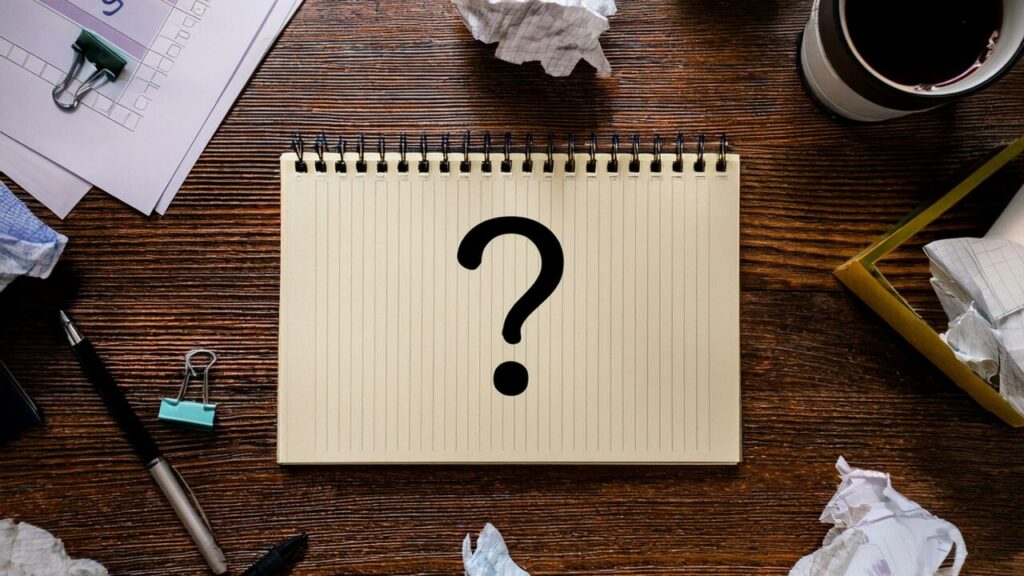
「副業中にケガしても、どうせ労災なんて出ないんでしょ?」
──こうした誤解、実はかなり根強く残っています。しかしこれは半分正解で、半分は間違いです。
まず、本業の労災保険は副業には適用されません
労災保険は、基本的に雇用主(事業主)と労働者の関係性を前提に成り立っています。
つまり、本業の会社で加入している労災保険は、その会社での業務中に限って適用されるもの。
副業中に起きた事故やケガには、本業の労災は一切関与しません。
副業で労災を受けたいなら「自分で加入」が前提
副業がアルバイトやパートなどの雇用契約であれば、その副業先が労災保険に加入していれば適用される可能性があります。しかし、フリーランスや個人事業主のように雇用契約がない形態の場合、国の制度における「特別加入」や、民間保険の活用が必要です。
よくある誤解とその真実
| 誤解 | 実際は… |
|---|---|
| 副業には労災が出ない | 条件を満たせば「特別加入」でカバー可能 |
| 会社が労災に入っていれば副業中も守られる | 副業先ごとに加入が必要。本業の労災は関係なし |
| フリーランスには労災は無縁 | 一人親方などの制度を使えば加入可能 |
つまり、「労災が出る・出ない」は、誰とどんな契約で働いているか、そしてどの保険制度に加入しているかによって大きく変わるということなんです。
「副業=労災対象外」と思い込んでいると、本来受けられるはずの補償を逃してしまう恐れがあります。誤解を避けるためにも、自分の働き方をしっかり把握し、必要な備えを整えておきましょう。
労災以外の補償手段も検討しよう

「特別加入で労災保険に入ればもう安心…?」
そう思ってしまいがちですが、実はそれだけではカバーしきれないケースもあります。
だからこそ、副業で働く人には労災保険に加えて“その他の補償手段”も併用することが重要なんです。
労災保険だけでは足りないこともある理由
労災保険の補償は、あくまで「業務上の災害」に限られます。つまり、
- プライベート中のケガや病気
- 通勤中以外の移動時の事故
- 対物・対人トラブルによる損害賠償責任
などは対象外となることが多いのです。
さらに、精神疾患や慢性的な職業病(腰痛・腱鞘炎など)といった「発症原因が明確でないケース」は、労災が適用されにくいことも。
民間保険で補える補償とは?
以下のような補償を民間でカバーすることで、より安心して副業に取り組めるようになります。
活用できる民間の補償制度
- フリーランス協会の賠償責任補償
┗ クライアントからの損害賠償請求や納品トラブルによる補償 - 所得補償保険(就業不能保険)
┗ 病気やケガで長期間働けなくなった際に収入をカバー - 傷害保険(通院・入院・手術の一時金)
┗ 業務外でも使えるため、日常生活でのリスクに備えられる
「労災+民間補償」の併用が最も安心
副業ワーカーにとっては、
- 業務中の事故 → 労災保険でカバー
- 日常生活や損害賠償 → 民間保険でカバー
という組み合わせが最適です。
特にフリーランス協会などの団体では、会員登録するだけで自動的に保険がついてくるプランも多く、コストパフォーマンスも良好。副業の収入規模に応じて選べるのも魅力ですね。
「どれか1つだけで完璧に守れる」保険は存在しません。
だからこそ、労災保険と民間の補償制度を組み合わせて、“自分専用の安全ネット”を作っていくことが今の時代に求められています。
【事例】副業中の事故で労災が役立ったケース

「本当に労災なんて使えるの?」
そんな不安を抱えるあなたにこそ読んでほしいのが、実際の体験談。
現場で起きたリアルな事故と、それに対する補償の流れを紹介します。
ケース1:配達中に転倒し、治療費と休業補償を受けた例
背景
40代・男性。副業で週末のみフードデリバリー(Uber Eats)をしていたところ、
配達中にバイクで転倒。足を骨折し、3ヶ月の通院・療養が必要に。
対応と補償内容
- 一人親方団体を通じて特別加入済み
- 労働基準監督署に事故報告・申請
- 療養補償(治療費全額)、休業補償(日額5,000円×約90日)を受給
「もし労災に入っていなかったら…生活が回らなかった」と語る本人の声からも、備えの大切さが伝わります。
ケース2:スキマバイト中の事故、業務委託だったため労災が使えなかった例
背景
30代・女性。副業でスキマバイトアプリを利用し、マンション清掃の仕事に従事。
作業中に共用廊下で転倒し、右手首を骨折。ところが…
結果と影響
- 利用したアプリは「業務委託契約型」だったため、雇用契約は成立していなかった
- 清掃業務中の事故ではあるが、労災保険の対象外とされる
- 治療費、通院、仕事を休んだ分の収入まで、すべて自己負担に
- 「まさか保険が効かないなんて…」と、契約形態による違いにショックを受ける
「雇われて働いたつもりだったけど、実は“業務委託”だったなんて思いもしなかった」
補足ポイント:スキマバイトの「契約形態」に注意!
副業でスキマバイトをしている方は、労災保険の適用があるかどうかを契約形態で必ず確認しましょう。
雇用契約ありなら…
→ 原則、労災保険が適用される(1日だけの勤務でもOK)
業務委託なら…
→ 自分で労災保険(特別加入)や民間保険に入っていなければ、補償なし!
アプリによっては、求人によって「雇用型」か「業務委託型」かが混在しているため、案件ごとに注意が必要です。特にギグワーク系・掃除代行アプリなどは委託型が多いため、事前チェックを欠かさないようにしましょう。
ケース3:在宅ワークでのトラブルはグレー判定に
背景
20代・男性。副業で動画編集を請け負っていたところ、
長時間の作業による腰痛が悪化し、整形外科を受診。
補償結果
- 特別加入済みだが「業務起因性が不明確」とされ、不支給に
- 精神疾患や慢性症状は因果関係の証明が難しく、ハードルが高い
- 民間の所得補償保険に加入していたため、そちらで給付を受ける
このように、「労災が適用されるか否か」は、働き方・事故の内容・証明の仕方に左右されます。
でもだからこそ、制度を理解して備えておくことが、未来の自分を守ることになるんです。
まとめ:副業でも安心できる保険加入をしよう
副業が当たり前になった今、「保険なんて本業だけで十分」なんて時代ではありません。
業務中の事故、通勤時のケガ、思わぬトラブル──副業の現場にも本業と同じようにリスクは潜んでいます。
そしてそのリスクに備える手段が、労災保険の特別加入制度や、民間の補償サービスなんです。
今回の記事でお伝えした重要なポイントは…
- 副業でも条件を満たせば国の労災保険に加入可能
- 自営業やフリーランスでも特別加入制度で補償を受けられる
- スキマバイトやアプリ経由の副業は契約形態に注意
- 労災保険だけでカバーできない部分は、民間の保険で補完するのが現実的
- 保険料や補償内容は、自分の働き方に応じて選ぶのがベスト
副業があなたの収入を支えてくれる大切な手段なら、
それを「守る」ための備えもセットで考えておきましょう。
保険に入っていたおかげで、「助かった」と思える未来を迎えるのか。
保険に入っていなかったせいで、「後悔する」未来を迎えるのか──
その分かれ道は、“今ここ”かもしれません。