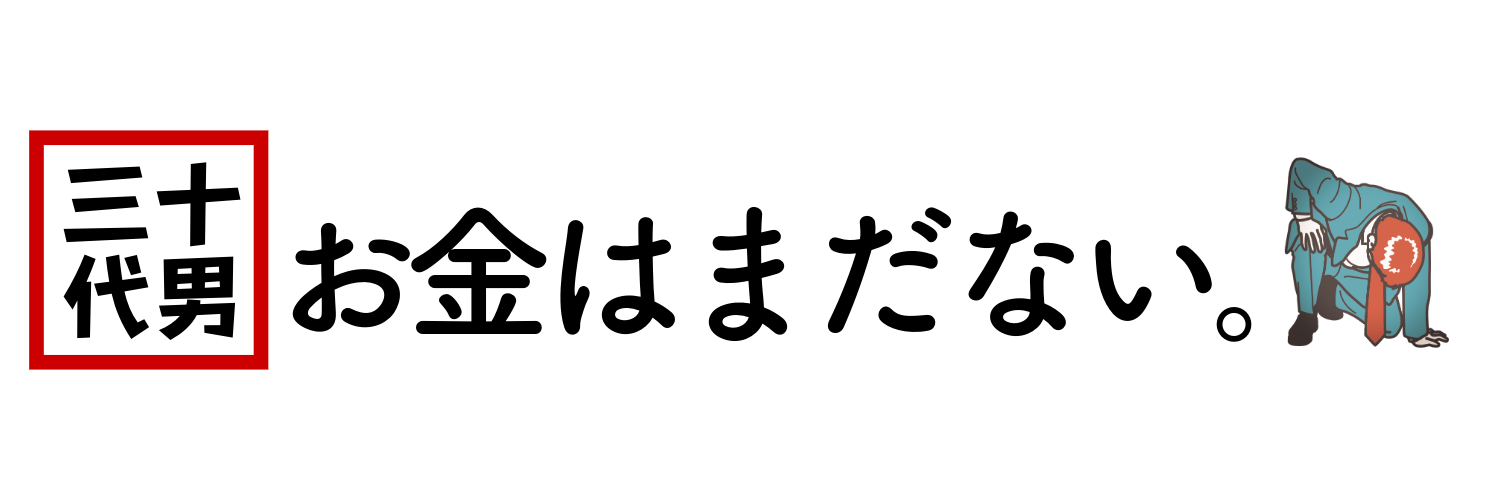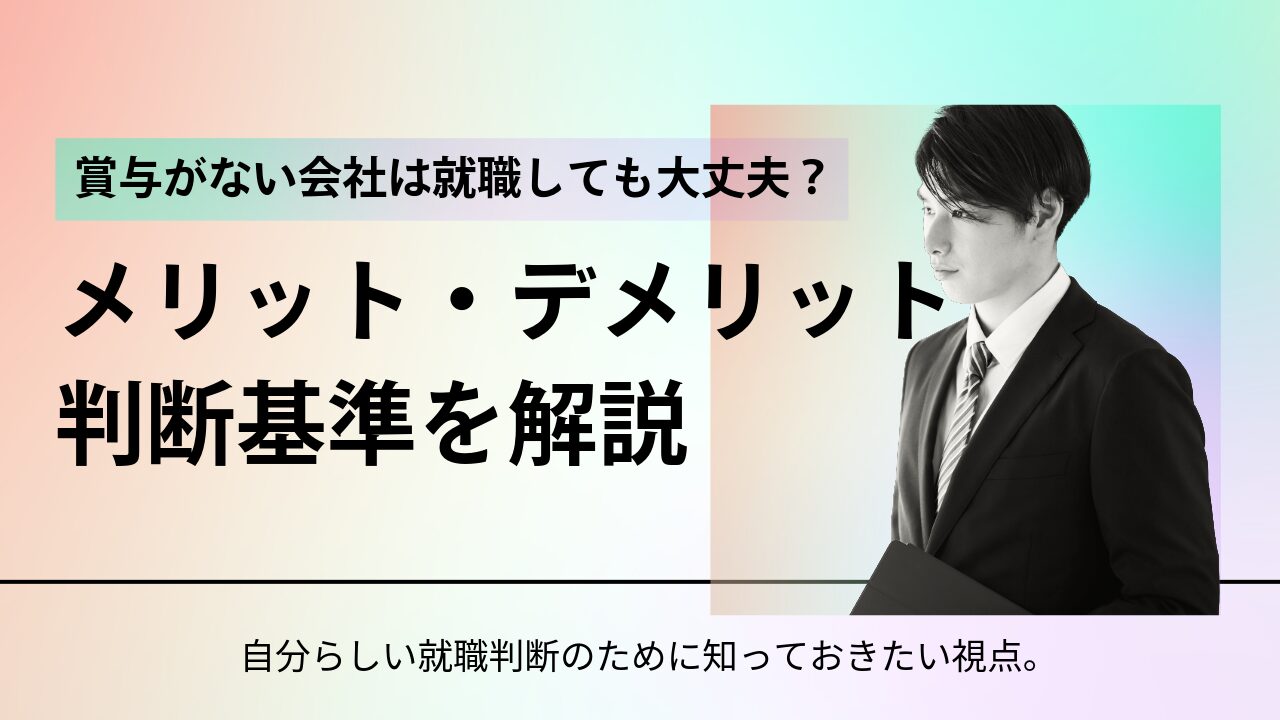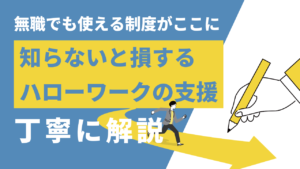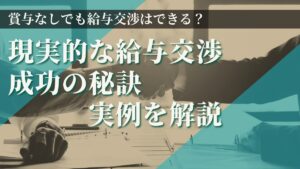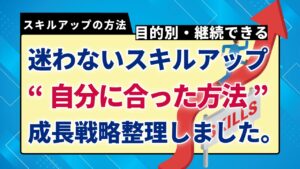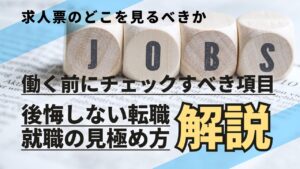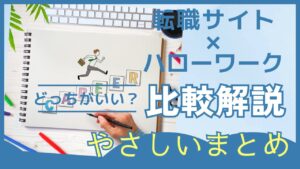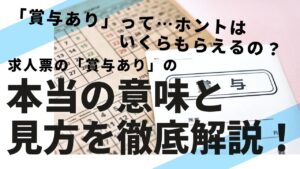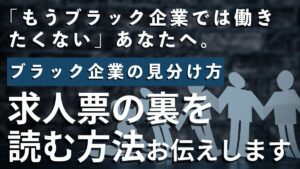「賞与がない会社って、本当に就職しても大丈夫なの?」——就職活動中や転職先を探す中で、こんな疑問に直面する人は少なくありません。給与体系は企業によってさまざまですが、賞与(ボーナス)の有無が人生設計に与える影響は大きいもの。この記事では、賞与がない会社に就職するメリット・デメリットを多角的に分析し、どんな選択があなたにとって後悔のない決断につながるかを深掘りしていきます!
賞与なしの企業に就職するのはアリ?結論とその背景

賞与がない=ブラック企業ではない
「賞与がない会社って、やっぱりブラックなのかな…?」そんなふうに考えてしまうのは自然な反応です。ですが、結論から言えば賞与がない=ブラック企業とは限りません。むしろ、現在では給与体系の多様化が進み、年俸制や月給への包括支給など、賞与という形を取らずに処遇している企業も少なくありません。
たとえば、IT・スタートアップ系の企業では、「年俸制」で給与を12等分して毎月支給する仕組みが一般的です。この場合、賞与としての一時金は出ませんが、その分、月給が高めに設定されていることが多く、「賞与がない=損している」とは一概には言えないのです。
また、業績が不安定な企業が無理に賞与を出すよりも、収支の透明性を重視して賞与を廃止しているケースもあります。これは、経営が不安定なわけではなく、むしろ「安定して給料を払いたい」という企業側の誠実さが表れていることも。
もちろん、中には「賞与がある」と求人に記載していながら、実際は寸志やゼロだった…という悪質なケースも存在します。ですがそれは“賞与がない”ことよりも“求人の透明性の欠如”が問題です。
つまり、賞与がない企業に出会ったときは、「その理由と給与の全体設計を見る」ことが大切。形式よりも中身に注目する視点を持つことで、就職の判断軸がぐっと明確になります。
月給制・年俸制との関係を理解しよう
賞与の有無を語るうえで、絶対に無視できないのが月給制・年俸制の違いです。就職や転職活動では「年収」で判断されがちですが、その内訳をしっかりと理解しておかないと、「思っていたより手取りが少ない!」といった落とし穴にはまりかねません。
まず、月給制の企業では「基本給+各種手当+賞与」で構成されることが多く、賞与が年に2回(夏・冬)支給されるのが一般的です。しかし、年俸制では、年収を12ヶ月(もしくは14ヶ月)で均等に割って支給するスタイルが主流。そのため、「ボーナス」という形ではもらえないけれど、毎月の支給額が多くなる傾向にあります。
たとえば、年収480万円で年俸制なら、毎月40万円支給される可能性があります。一方、同じ年収でも月給制で賞与が60万円×2回なら、月の支給額は約30万円前後になります。このように、賞与の有無は「見せ方」の問題であり、手取りや実質的な収入額は同等ということも多いのです。
また、賞与は「業績連動型」であるケースが多いため、業績が悪ければゼロ…なんてことも。一方、年俸制は契約時点で支給額が決まっているため、安定した収入が見込めるという点で魅力を感じる人もいるでしょう。
結論としては、給与体系を正しく理解し、「賞与がない=給料が低い」ではなく、全体でいくら得ているか・安定性はどうかに目を向けることが大切です。
賞与の代わりに福利厚生が充実している場合もある
賞与がないと聞くと「やっぱり損なのでは?」と感じてしまうかもしれませんが、その分、福利厚生が手厚く用意されている企業もあります。とくにベンチャー企業や外資系企業では、賞与制度を持たない代わりに、日常生活や将来設計に直接プラスになる制度を整えているケースが増えています。
たとえば以下のような福利厚生があります:
- 家賃補助や住宅手当
賞与の代わりに、月々の生活負担を軽くしてくれる制度。家賃の3割〜5割を補助する企業もあります。 - リモートワーク手当・通勤手当
在宅勤務環境の整備や、通勤費の全額支給など、働き方の自由度を支える支援。 - 確定拠出年金・退職金制度
一時的な賞与よりも、将来的な資産形成を重視する設計。節税効果もあります。 - 育児・介護支援制度
出産育児一時金や、保育園費用補助、介護休暇の取得実績など、ライフステージの変化に寄り添った制度。
これらは一見すると「見えにくい報酬」ですが、長期的に見れば賞与以上の価値を持つことも少なくありません。実際、「毎年数十万円の賞与」よりも、「毎月3万円の住宅手当」の方がトータルで得になることもあるのです。
企業によっては、社員が利用できる施設やサービス(スポーツジム、社員食堂、旅行補助など)を充実させて、給与以上の満足度を提供している場合もあります。ですから、賞与の有無だけで判断せず、福利厚生の中身と質を比較検討する視点も持つことがとても重要です。
賞与なし企業のメリットとデメリットとは?

メリット:毎月の給与に反映されている場合がある
賞与がない企業でも、その分を月給に上乗せして支給しているケースは少なくありません。これは「年収総額は変えずに、給与の配分方法を調整している」スタイルです。つまり、年収ベースで見ると賞与のある会社とほとんど差がない、あるいはむしろ手取りが安定しているという可能性もあります。
たとえば、賞与ありの企業では年収500万円のうち賞与が100万円(年2回)だった場合、月収は約33万円前後。しかし、賞与なしの企業で同じ年収の場合、月収は41〜42万円に設定されることが多く、毎月安定した収入が得られるという安心感があります。
この「月額安定型」は、特に以下のような人にとってメリットとなります:
- 賃貸契約などで毎月の収入証明が必要な人
- 家計を月単位でしっかり管理したい人
- ボーナス依存型の生活スタイルを避けたい人
さらに、賞与が業績に左右されることがない=収入のブレが少ないため、ライフプランを立てやすいという利点も。たとえば、ローンや教育費の計画を立てる際に、「いつ・いくら入ってくるか」が明確になっていることは、大きな安心材料となります。
つまり、賞与がないことが必ずしもマイナスではなく、給与の設計次第ではむしろ堅実で計画的な収入形態とも言えるのです。
デメリット:モチベーション維持が難しくなる可能性
賞与がない企業において、多くの人が直面しやすいのがモチベーションの維持が難しくなる問題です。ボーナスは、単なるお金以上の意味を持っています。たとえば「成果が認められた証」「努力に対するご褒美」として、精神的な報酬の役割を果たしているのです。
たとえば、営業職や企画職などで、「目標達成したから夏の賞与が増えた!」といった経験は、次の仕事への活力になります。逆に、賞与がない場合は、「どれだけ頑張っても給与は同じ」と感じてしまい、やる気が空回りしてしまうケースもあります。
特に、評価制度が不透明な会社や、フィードバックの機会が少ない職場では、賞与がないことで「見えない評価の低さ」を疑ってしまうことも。社員からすると、「ちゃんと見てもらえてるのかな?」「頑張っても意味ないかも…」という心理的不安が生じやすいのです。
さらに、同年代の友人や同業他社の社員が「賞与◯ヶ月分出た!」と話しているのを聞くと、自分だけ取り残されたような気持ちになることも。「評価される機会が少ない=承認欲求が満たされにくい」ことは、働き続けるうえで地味ながら大きなストレス源となります。
もちろん、賞与の代わりにインセンティブや評価面談、昇給制度が整っていれば話は別ですが、それがない場合はやりがいの低下=離職率の上昇にもつながりやすいと言えます。
実際の生活設計に与える影響とは
賞与がないことは、感情的な問題だけでなく、実生活やライフプランの設計にも大きく影響してきます。特に、年収の中に賞与が含まれていない場合、予期せぬ出費への備えや資産形成に影響を及ぼす可能性があるのです。
たとえば、賞与がある場合には、「旅行資金に充てよう」「車のローンの一括返済に使おう」「教育費の積み立てにまわそう」など、まとまったお金をライフイベントに使う計画が立てやすくなります。一方、賞与がないと、毎月の給与の中で全てをまかなう必要があり、余剰資金の捻出が難しくなることも。
また、住宅ローンを組む際にも、金融機関が賞与込みの年収を審査に使うことがあります。賞与がない場合、「返済能力が低く見積もられる」可能性があり、希望する金額の融資が受けられないケースもあるのです。
さらに、賞与のある企業では、年末調整後にまとまった税還付を受けやすくなる傾向もあります。これは扶養控除や生命保険控除などが影響する部分ですが、賞与があるとその分、税金の還付が大きくなりやすい。逆に賞与なしの給与構成では、年間の納税・控除のバランスが変わるため、手取りに地味な差が生まれることもあります。
ただし、ここで重要なのは「収入の総額ではなく、お金の使い方・貯め方をどう設計するか」という視点です。賞与がなくても、月給が高めならば、その分を積み立ててボーナスのように運用することも可能。つまり、「自分で“見えない賞与”をつくる」という発想があれば、生活への不安はぐっと減るのです。
賞与なし企業を選ぶべき人の特徴とは

安定よりも柔軟な働き方を重視する人
賞与がない会社に向いているのは、何よりも「毎年決まった賞与」よりも自分らしい働き方や自由な時間の使い方を重視する人です。たとえば、近年増加しているスタートアップやITベンチャー企業では、固定賞与よりも「成果主義+フレックス+リモートワーク」など、柔軟性を重視した働き方が広がっています。
このような職場では、賞与という制度をあえて設けずに、代わりに自由度の高い働き方や高い裁量権を提供しています。たとえば、勤務時間や場所を選べる「フルフレックス制度」や、「副業OK」「週休3日制度」などがその例です。
「がっちり固定された報酬より、変化やチャレンジに価値を感じる」タイプの人にとっては、賞与がない代わりに得られる自由や刺激は、大きな魅力になりえます。
また、外資系企業では、賞与を基本的に廃止し、その分、裁量労働制や職務等級による昇格チャンスの多さでやる気を引き出す文化が一般的。その結果、「働いた分だけリターンを得たい」「結果に責任を持ちたい」と考える人にはピッタリの環境となります。
賞与の有無よりも、「どう働き、どう評価されたいか?」を重視する人にとっては、むしろ賞与に縛られない会社の方がマッチする可能性が高いのです。
インセンティブ制度や評価制度に納得できる人
賞与がなくても「納得できる評価制度がある」のであれば、その会社は選択肢として十分アリです。特に、インセンティブ制度や定期的な昇給評価がしっかりしている企業においては、賞与に頼らずともモチベーション高く働ける環境が整っています。
たとえば営業職やSaaS企業などでは、成果に応じたインセンティブ(歩合)が月ごと・四半期ごとに支給されるケースがあります。この場合、ボーナスという名目ではないものの、自分のパフォーマンスがダイレクトに収入へ反映されるため、頑張りがいがあると感じる人も多いです。
また、評価制度が透明で、定期的なフィードバックやスキル査定がある企業では、「年に1〜2回の賞与」よりも、日常的に評価されているという実感を得やすくなります。
こうした環境では、「賞与のタイミングまで頑張る」のではなく、「日々の積み重ねでしっかり評価される」ため、評価の納得感=職場への信頼感にもつながりやすいのが特徴です。
さらに、「目標設定→中間評価→最終評価→昇給・昇格」というサイクルが年に複数回ある企業では、“成長の実感”が高く、賞与以上の満足感を得られることもあります。賞与が一律で支給されるよりも、自分の努力や成果が正当に可視化される方が嬉しいという人には、こうした制度の方がずっと相性がいいでしょう。
つまり、「どんな基準で評価されるのか」「頑張った分はどう還元されるのか」に納得できる人なら、賞与がなくても充実した働き方ができる可能性は高いのです。
副業や資産運用など他の収入源がある人
賞与に頼らなくても生活を安定させられる人——それは、副業や資産運用など複数の収入源を持っている人です。現在は「会社からの給料一本」に依存しない働き方や生計スタイルが浸透しつつあり、特に若い世代やミドル世代を中心に「ボーナスがなくても問題ない」という価値観が広がっています。
たとえば、副業でブログやYouTube運営、Webライター、スキル販売(ココナラ・タイムチケット等)などを行っている場合、月数万円〜十数万円の収入がある人も少なくありません。こうした人にとっては、「ボーナスという不確定な報酬より、自分でコントロールできる副業収入の方が安心できる」という考えも成り立ちます。
また、つみたてNISAやiDeCo、不動産投資、配当株などによる中長期の資産形成を行っている人は、賞与に頼らないライフプランを描いていることが多いです。ボーナスがなくても、毎月一定額を自分の投資先に回しておけば、「将来的な賞与の代替資産」を自ら作っているとも言えるのです。
こうしたライフスタイルは、「会社に収入を依存しすぎない」「自分で経済的な安心を作り出す」という意味で非常に合理的。賞与の有無に一喜一憂する必要がないため、精神的にも安定しやすいです。
つまり、自分自身で収入のポートフォリオを組める人にとって、賞与がない会社は「年収設計に柔軟性がある会社」として魅力的に映ることもあります。
入社前にチェックすべき5つのポイント

賞与なしの理由を確認する
まず絶対に確認しておくべきなのが、なぜ賞与がないのか、その理由です。企業によって「賞与を出せない理由」ではなく、「出さない方針」であるケースもあります。たとえば、年俸制を採用しているから、インセンティブで調整しているから、あるいは福利厚生や昇給制度に重きを置いているからなど、“制度的な理由”で賞与を設けていない場合は、特に問題ではありません。
しかし、問題なのは「業績が悪化して賞与が廃止された」「制度はあるけど実質ゼロが続いている」といったケースです。このような会社では、経営の不透明さや先行きの不安が疑われます。
確認すべきポイントは以下の通り:
- 賞与の制度が存在するか?(社内規定、労働契約書など)
- 制度はあるが、実績として支給されているか?(平均支給額など)
- 評価や査定はどのように行われているか?
- 「賞与なし」の代わりにどんな処遇があるか?(月給上乗せ、インセンティブなど)
企業の面接や説明会で「賞与はありません」と言われたときには、遠慮せずに“理由”と“代替する制度”を尋ねることが大切です。そこで納得できる説明があるかどうかが、判断のカギになります。
年収ベースで待遇を比較する
「月収が高い=条件が良い」と思いがちですが、就職や転職時に本当に注目すべきなのは“年収ベースでの総額”です。賞与がない企業の場合、つい「毎月の手取りが多いから良さそう」と判断しがちですが、年間を通じてどれだけの報酬が支払われるのかを正確に把握しなければ、後々ギャップに苦しむことになります。
たとえば、A社は月収32万円・賞与年2回(計80万円)、B社は月収38万円・賞与なしだったとします。一見するとB社の方が魅力的に映りますが、年収に換算すると:
- A社:32万円×12ヶ月+80万円=464万円
- B社:38万円×12ヶ月=456万円
この場合、年収ベースではA社の方が高いことになります。さらに、昇給ペースや福利厚生、社会保険料の負担額なども加味すると、実質的な手取りや生活の安定性に差が出てくるのです。
また、賞与がある会社では、業績好調時に「特別賞与」や「決算賞与」が支給される可能性もあります。一方で、賞与がない代わりに毎月の給料に含められている場合、その分は固定化されており、変動の余地が小さいことも。
こうした違いを見抜くためには、「月給だけで比較しない」「賞与がなくても年収として満足できるか」を確認する視点が不可欠です。給与明細のサンプルをもらえる場合は、手取りベースで比較することもおすすめです。
昇給制度やキャリアアップの仕組みを見る
賞与がない企業を検討するうえで重要なのは、昇給やキャリアアップのルートが明確に用意されているかどうかです。ボーナスが支給されない分、毎年の基本給アップや等級制度の存在が、将来的な収入の柱になります。
注目すべきポイントは以下のとおりです:
- 昇給は年に何回あるか?(例:年1回 or 半期に1回)
- 昇給の幅はどのくらいか?(定額昇給か、等級ごとの幅があるか)
- 評価制度は定量評価(数値)か定性評価(態度や行動)か
- キャリアパスはどのように描かれているか?(例:メンバー→主任→係長→課長)
たとえば、賞与がない代わりに、半期に一度必ず給与改定の機会がある会社や、スキルアップに応じて職能手当が増える制度を採用している企業では、「自分の成長が年収アップに直結する」という感覚を持てます。
また、キャリアアップのロードマップが社内で公開されている企業では、自分の数年後の収入や役職の見通しが立てやすく、賞与がなくても“長期的な報酬設計”が安心材料になるのです。
逆に、昇給が明文化されておらず、「なんとなく毎年上がる」「上司の気分次第」などの曖昧なルールが存在する企業では、賞与がないことがリスク要因に転じます。
つまり、賞与の有無だけでなく、「年々の収入がどう積み上がっていくか」「努力や成果がどのように昇給に結びつくか」をきちんと見ておくことで、将来的な不安を大きく減らすことができるのです。
会社の定着率・離職率を調べる
賞与がない企業を検討する際、その会社に長く働いている人がどれだけいるのか=定着率や離職率を必ず確認しましょう。なぜなら、賞与制度がないことに不満を感じている社員が多い企業では、人の出入りが激しく、組織の安定性が欠けている可能性があるからです。
一般的に、離職率が高い企業には以下のような傾向があります:
- 評価や報酬制度に納得感がない
- キャリアパスが描きにくい
- 福利厚生や労働環境が劣悪
- 経営陣の説明責任や透明性に欠ける
こうした問題が「賞与なし」という一点にとどまらず、全体の労働環境の質に関わっていることが多いのです。
定着率を調べる方法としては:
- 「四季報」や「就職四季報」などで新卒3年以内の離職率を確認
- 転職サイト(OpenWork、エン カイシャの評判など)で社員のリアルな口コミをチェック
- 面接で「平均勤続年数」や「離職理由」を直接聞く
- SNSや匿名掲示板で、元社員の声をリサーチ
特に口コミサイトでは、「賞与がなくても給与に納得している」「むしろ賞与制度がない分、業績に左右されず安心」という声が多ければ、ポジティブな要素と捉えられます。一方、「賞与は制度上あるけど、出たことがない」「評価制度が曖昧で昇給も遅い」という声が多ければ、注意が必要です。
賞与の有無よりも大切なのは、「なぜその制度なのか」と「社員が納得して働けているか」。定着率・離職率は、その会社の“働きやすさ”や“報酬設計の納得感”を表す間接的な指標なのです。
実際の社員クチコミや転職サイトを活用する
企業の賞与制度が実際にどう機能しているのかを知るために、転職サイトや社員クチコミの情報は非常に有効なリサーチ手段です。会社説明会や面接ではなかなか本音を聞き出せない部分も、匿名の口コミサイトでは赤裸々に語られていることが多く、“表に出ない真実”が見えてくるのです。
活用すべき主なプラットフォームは以下のとおりです:
- OpenWork(旧Vorkers)
評価制度、年収の実態、賞与支給の有無、働きやすさなどを職種別・年代別に確認できます。 - エン カイシャの評判(旧ライトハウスの評判)
社員・元社員による具体的なコメントが多く、賞与や昇給についての“実感値”が見えてきます。 - 転職会議、、Indeed企業レビュー
ネガティブ・ポジティブ両面の情報が載っているため、バランスをとって判断可能。
たとえば、「求人には“賞与あり”とあるのに、実際は数千円程度だった」「制度はあるが業績次第でゼロが当たり前」などの声があれば、求人情報だけではわからないリスクが見えてきます。
また、「賞与がないけど、その分基本給が高い」「福利厚生が超充実していて納得している」などの口コミも、賞与がない会社に対して前向きな評価がされているかどうかの判断材料になります。
口コミ情報は“すべてが正しいわけではない”ことも念頭に置きつつ、複数の情報源を照らし合わせることで、求人票からは見えない“現場の空気”を把握することができます。
賞与の有無だけに目を奪われず、働きがいや制度の透明性、社員の納得感を確認することで、より信頼できる企業選びができるのです。
賞与なし企業への就職に迷うあなたへ

「賞与あり=正解」ではない
「賞与がある会社の方が“ちゃんとしてる”」「ボーナスがないなんて非常識では?」と思ってしまう気持ち、よくわかります。しかし、現代の働き方や報酬体系は多様化しており、賞与があること=正解、賞与がないこと=ハズレ、とは言い切れない時代になっているのです。
たとえば、賞与が出ても「寸志レベル(数千円~数万円)」「業績次第でゼロ」「評価が不透明で不満が多い」といったケースは珍しくありません。一方で、賞与はないけれど、月給が高めに設定されていたり、昇給・昇格のルールが明確で納得感がある企業も多数存在します。
また、「賞与の期待感」がかえってプレッシャーやストレスになる人もいます。「年末まで頑張らなきゃ…」「ボーナス査定が気になって上司に媚びる」など、本質とはズレた評価文化に悩む人も少なくないのです。
つまり、賞与の“有無”よりも大切なのは、「その会社の評価制度や報酬設計が、自分にとって納得できるかどうか」。見た目の制度に振り回されず、自分の価値観と合っているかどうかで判断することが、後悔しない選択につながります。
大切なのは“総合的な納得感”
賞与があるかどうか——確かに気になるポイントです。でも、最も重要なのは、その企業で働くことに対して「総合的に納得できるか」どうかです。収入、働き方、人間関係、評価制度、成長環境……これらすべてが絡み合って、「ここで働いて良かった」と思えるかどうかが決まります。
たとえば、賞与があっても:
- 昇給がまったくない
- 残業代が出ない
- 休日が少なく、有休も取りづらい
- 上司の評価基準が不透明
というような職場であれば、賞与の金額以上にストレスが溜まり、結局は転職を考えることになるかもしれません。
一方で、賞与はないけれど:
- 給与体系がシンプルで明快
- 昇給が定期的にある
- 評価制度に納得感がある
- 働きやすく、プライベートとの両立もしやすい
そんな会社なら、「長く働きたい」「ここでキャリアを築きたい」と思えるでしょう。
企業を見るときは、「賞与」という1点だけを取り出して比較せず、“トータルで自分にフィットしているか”という視点を持つことが、後悔しない職場選びの秘訣です。
納得感は、人によって違います。大切なのは、他人の基準ではなく、あなた自身の価値観で「ここなら頑張れそう」と思える職場かどうかを見極めることです。
自分の人生設計に合った選択をしよう
賞与の有無は、たしかに気になるポイント。でも、もっと大切なのは、「自分の人生設計にその会社が合っているかどうか」です。たとえば、あなたが家族との時間を大切にしたいのか、バリバリ出世していきたいのか、起業を目指しているのか——どんな未来を描いているかによって、理想の職場は大きく変わります。
もしあなたが安定した収入を望むなら、年俸制で月額が一定の会社は家計管理がしやすく合っているかもしれません。逆に、「成果で収入を変えたい」「短期間で高収入を得たい」という人には、賞与やインセンティブが明確に支給される企業の方が合っている可能性もあります。
また、育児・介護などライフステージの変化を視野に入れているなら、賞与よりも福利厚生や柔軟な働き方を提供しているかどうかが重要になってきます。
「ボーナスがないと不安」という感覚も自然ですが、それを解決する手段は他にもあります。たとえば:
- 月給に上乗せされた年俸制
- 資産運用による“自分で作るボーナス”
- キャリアアップによる収入の底上げ
つまり、会社からの賞与だけが、あなたの人生を支える選択肢ではないのです。
あなたがどんな生活をしたいか、どんな働き方を求めているか。
それにしっかりと向き合ったとき、賞与の有無は「判断軸のひとつ」に過ぎないことに気づくはずです。
企業選びとは、自分自身との対話でもあります。「どんな働き方が、どんな未来をくれるのか?」——その答えが見つかったとき、納得のいく選択ができるようになります。